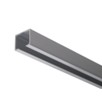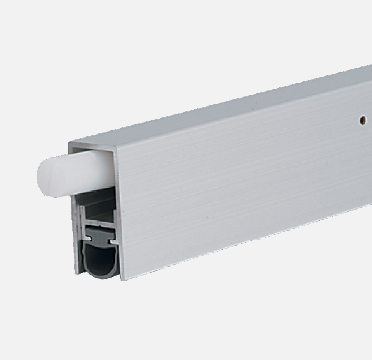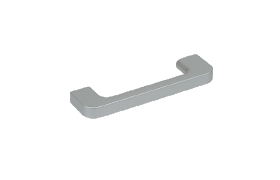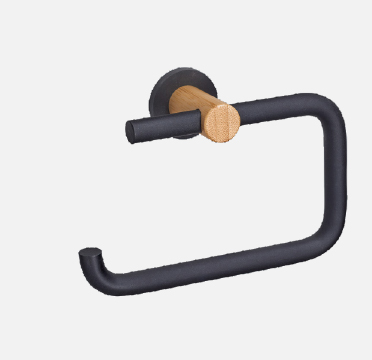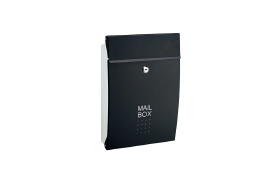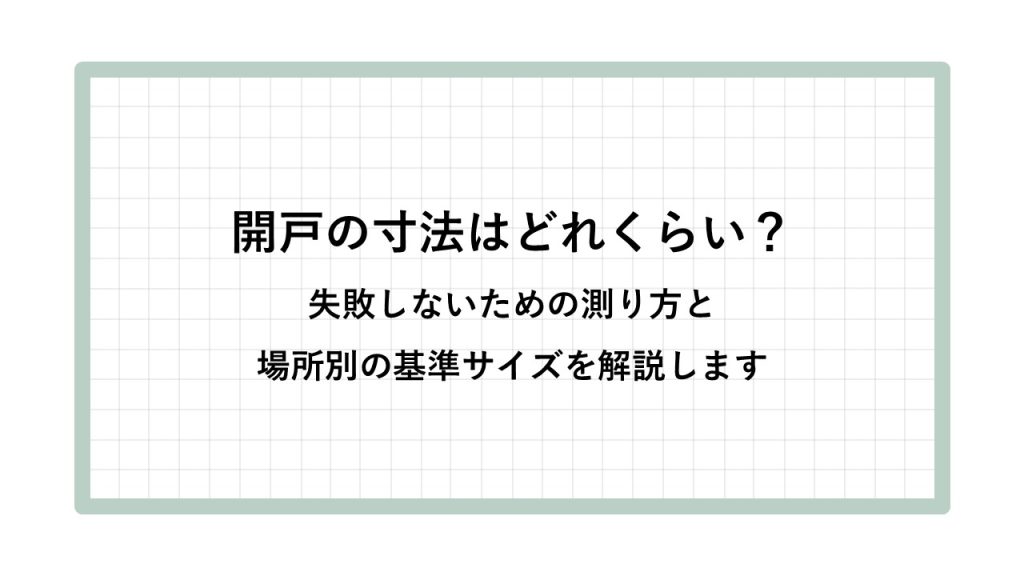家の新築やリフォームにおいて、何気なく決めてしまいがちな「開戸の寸法」。
しかし、この寸法を一つ間違えるだけで、家具の搬入ができなかったり、車椅子での通行が困難になったりと、後々の生活に大きな影響を与えかねません。
「標準サイズで」と考えていても、どこを基準に測れば良いのか、どのくらいの幅があれば十分なのか、迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
この記事では、そうした失敗や後悔を防ぐために知っておきたい、開戸の寸法の基本を徹底解説します。
ご自身でできる正しい測り方から、玄関やトイレといった場所別の適切なサイズ、さらには将来を見据えたバリアフリーの基準まで、この記事を読めば全てが分かります。
まずは、寸法選びの土台となる基本的な考え方から確認していきましょう。
開戸の寸法における基本的な考え方
開戸の寸法について考えるとき、単にドア本体の大きさを測れば良いというわけではありません。快適で安全な住環境を実現するためには、いくつかの基本的な知識を押さえておくことが重要です。
特に「幅」「高さ」「厚さ」の3つの要素と、「枠外寸法」「有効開口寸法」という言葉の意味を理解することが、失敗しないドア選びの第一歩となります。
幅・高さ・厚さの3つの要素
開戸の寸法は、主に「幅」「高さ」「厚さ」の3つの要素で構成されています。幅は人が通るために最も重要な寸法であり、高さは頭をぶつけずにスムーズに出入りできるかを左右します。
厚さは、ドアの強度や防音性、断熱性に関わる要素です。これらのバランスが、ドアの使い勝手や性能を決定づけます。
「枠外寸法」と「有効開口寸法」の違い
ドアの寸法を検討する上で、特に注意したいのが「枠外寸法」と「有効開口寸法」の違いです。
| 用語 | 説明 |
| 枠外寸法 | ドアの枠を含めた、壁に取り付ける部分全体の大きさを示します。リフォームで壁を工事せずにドアを交換する場合、この寸法が非常に重要になります。 |
| 有効開口寸法 | ドアを実際に開けたときに、人や物が通れる部分の純粋な幅のことを指します。車椅子での通行や大きな家具の搬入を考える際には、この寸法を必ず確認する必要があります。 |
カタログなどに記載されているドアのサイズが、どちらの寸法を指しているのかを正しく理解していないと、「購入したドアが枠に収まらない」「想定していた幅より狭くて車椅子が通れない」といったトラブルの原因になります。
自分でできる!開戸の寸法の測り方

ご自宅のドアを交換したい、あるいは新築で寸法を検討する際に、現状のサイズを正確に把握することは非常に大切です。
ここでは、専門家でなくても自分でできる、開戸の寸法の基本的な測り方をご紹介します。測り始める前に、いくつかの道具を準備しましょう。
準備するもの
正確な測定のためには、以下の道具を準備することをおすすめします。
準備するもの
・メジャー(金属製のもの)
・水平器(任意ですが、あるとより正確に測れます)
・筆記用具とメモ帳
布製のメジャーは伸び縮みして誤差が出やすいため、必ず金属製のメジャーを使用してください。
幅の測り方:3点を計測する
ドアの幅を測る際は、扉の枠の内側を計測します。長年の使用で家が歪んでいる可能性も考慮し、必ず上部・中央・下部の3カ所を測るようにしましょう。
もし3カ所の寸法が異なる場合は、最も小さい数値を基準として採用するのが一般的です。これにより、新しいドアを取り付ける際に「枠に入らない」という事態を防ぐことができます。
高さの測り方:枠の内側を測る
高さも幅と同様に、ドア枠の内側を測ります。床からドア枠の上部の内側までの距離を計測してください。このとき、メジャーが斜めにならないよう、まっすぐに保つことが正確な測定のコツです。敷居がある場合は、敷居の上からの高さを測ります。
ドアの厚さを測る際の注意点
ドアの厚さは、ドア自体の側面を測ります。デザインによっては表面に凹凸があるドアもありますが、最も厚い部分を基準にするのではなく、枠に収まる部分の厚さを正確に測ることが重要です。
この厚さが合わないと、ドアがきちんと閉まらなくなる原因となります。
【場所別】一般的な開戸の寸法まとめ
開戸の寸法は、設置される場所の用途によって求められるサイズが異なります。ここでは、玄関、リビング、トイレなど、代表的な場所ごとに一般的な開戸の寸法をまとめました。ご自宅のドア選びの参考にしてください。
玄関ドア:家の顔となる重要な寸法
玄関ドアは、人の出入りだけでなく、防犯性や断熱性も求められる重要な建具です。一般的な戸建て住宅の場合、幅は80cm〜90cm程度が主流です。この幅があれば、荷物を持っていてもスムーズに出入りが可能です。高さは、現在の主流は200cm以上ですが、古い住宅では180cm程度のこともあります。
リビングドア:人の出入りや家具の搬入を考慮
家族が集まるリビングのドアは、開閉の頻度が高く、家具や家電の搬入経路にもなるため、やや広めの寸法が推奨されます。一般的な幅は80cm前後が目安です。採光を考えてガラス面積の大きいデザインを選んだり、開放感を重視して天井までの高さがある「ハイドア」を選択したりするケースも増えています。
トイレ・洗面所のドア:プライベート空間の基準
トイレや洗面所などのプライベートな空間では、他の居室よりも少し幅の狭いドアが使われることが一般的です。有効開口幅で60cm程度あれば、人の出入りには問題ありません。
ただし、将来的に介護が必要になったり、車椅子での利用を想定したりする場合は、より広い幅を確保しておく必要があります。
寝室・子ども部屋のドア:使いやすさを重視
寝室や子ども部屋など、個室のドアはリビングと同様に80cm前後の幅が一般的です。ベッドなどの大型家具を搬入することも考慮し、ある程度の幅を確保しておくと安心です。以下に、一般的な室内ドアの寸法例をまとめました。
| 項目 | 寸法例 |
| 枠外幅 | 735mm〜875mm |
| 製品高 | 2045mm程度 |
| 有効開口寸法 | 610mm〜750mm |
開戸の寸法を決める際の重要なポイント
開戸の寸法は、単に好みだけで決められるものではなく、法律や安全性、そして住まい全体のバランスを考慮して決定する必要があります。ここでは、寸法を決める上で特に重要となるポイントを3つ解説します。
建築基準法で定められた最低限の寸法
日本の建築基準法では、火災などの非常時に備え、居室の出入り口について最低限の寸法が定められています。具体的には、幅75cm以上、高さ180cm以上とされています。
これは安全な避難経路を確保するための基準であり、新築や大規模なリフォームの際には必ず守らなければならない規定です。
将来を見据えたバリアフリー対応の寸法

高齢化社会の進展に伴い、住宅のバリアフリー化が重要視されています。特に車椅子での生活を想定する場合、ドアの寸法は非常に重要です。
JIS規格で定められた車椅子の幅は、手動式で63cm以下、電動式で70cm以下です。車椅子でスムーズに通行するためには、ドアの有効開口寸法として最低でも80cm以上を確保することが推奨されています。新築やリフォームの際には、現在の利便性だけでなく、将来のライフスタイルの変化を見越した寸法計画を立てることが賢明です。
廊下の幅や周辺のスペースとのバランス
開戸は、ドアを開く際に手前か奥に半円状のスペース(軌跡)が必要になります。そのため、ドアの寸法だけでなく、廊下の幅や、ドアを開けた先に家具などを置くスペースがあるかどうかも考慮しなければなりません。
ドアを開けたら廊下が塞がれてしまう、あるいは壁や家具にぶつかって全開にできない、といったことがないように、周辺の環境とのバランスを考えた上で最適な寸法を選ぶことが大切です。
まとめ
開戸の寸法は、住まいの快適性と安全性を大きく左右する重要な要素です。この記事で解説した寸法の測り方や場所ごとの基準、そして法律やバリアフリーといった専門的な観点を参考に、ご自身のライフスタイルに最適なドアを選びましょう。
後悔しない家づくりのために、寸法の計画は慎重に行ってください。