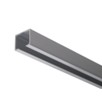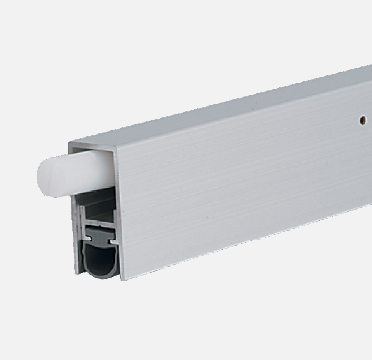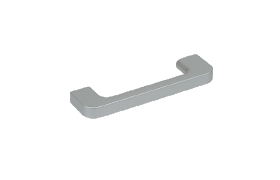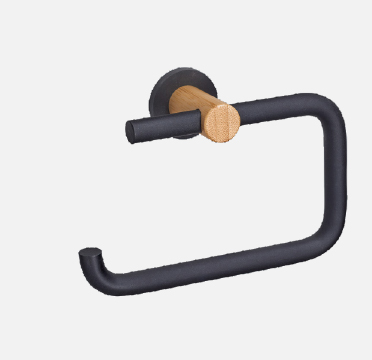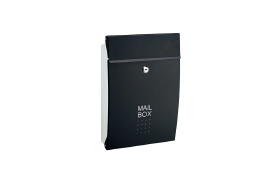新築やリフォームを計画する際、間取りやインテリアにこだわりを持つ方は多いですが、ドア選びも住まいの印象や暮らしの快適さを左右する重要なポイントです。
特に、多くの住宅で採用されている「開戸」には、さまざまな種類があり、どれを選べば良いか迷ってしまうことも少なくありません。
この記事では、開戸の基本的な知識から、主な種類、それぞれのメリット・デメリット、そして後悔しないための選び方のポイントまで、分かりやすく解説していきます。ご自身の住まいにぴったりのドアを見つけるために、ぜひ最後までご覧ください。
開戸とは?引き戸との基本的な違い
住宅に使われるドアは、開閉方法によって大きく「開戸(ひらきど)」と「引き戸(ひきど)」の2種類に分けられます。ドア選びで後悔しないためには、まずこの2つの基本的な違いを理解しておくことが大切です。それぞれの特徴を知り、ご自身の住まいにどちらが適しているか考えてみましょう。
押したり引いたりして開閉する「開戸」
開戸は、蝶番(ちょうつがい)を軸にして、ドアを前後に押したり引いたりして開閉するタイプのドアです。欧米の住宅で古くから使われており、日本でも洋室のドアとして広く普及しています。気密性や遮音性に優れているのが特徴で、プライベートな空間である寝室や書斎などに適しています。デザインのバリエーションが豊富な点も魅力の一つです。
横にスライドさせて開閉する「引き戸」
一方、引き戸は、溝やレールの上を戸が横にスライドして開閉するタイプのドアです。日本の伝統的な住宅で襖(ふすま)や障子(しょうじ)に使われてきた形式で、現代の住宅でも和室や収納スペース、バリアフリーを意識した空間などで活用されています。開閉のために前後のスペースを必要としないため、空間を有効活用できるのが大きなメリットです。
開戸の主な種類とそれぞれの特徴
一口に開戸といっても、扉の枚数や開き方によっていくつかの種類に分かれます。ここでは、代表的な3種類の開戸の特徴について、それぞれ詳しく見ていきましょう。それぞれの特徴を理解することで、よりご自宅の用途やデザインに合ったドアを選ぶことができます。
| 種類 | 特徴 | 主な用途 |
| 片開き戸 | 1枚の扉で開閉する最も標準的なタイプ。 | 部屋の出入り口、トイレ、収納など |
| 両開き戸 | 2枚の同じ大きさの扉が中央から左右に開く。 | リビング、広い間口の収納など |
| 親子ドア | 大小2枚の扉で構成される。 | 玄関、リビングなど |
最も一般的でシンプルな「片開き戸」
片開き戸は、1枚の扉が左右どちらか一方に開く、最もスタンダードなタイプの開戸です。 構造がシンプルで設置しやすく、比較的コストを抑えられるため、住宅内のあらゆる場所で採用されています。
例えば、個室のドアやトイレ、洗面所など、プライベートな空間の間仕切りとして最適です。デザインや色、素材の選択肢が非常に豊富なため、インテリアに合わせて選びやすいのも嬉しいポイントです。
開放感と高級感を演出する「両開き戸」
両開き戸は、「観音開き」とも呼ばれ、2枚の扉が中央から左右対称に開くタイプのドアです。 開口部を広く取れるため、開放感があり、空間を豪華でエレガントな印象に見せることができます。大きな家具や家電を搬入する際にも便利です。
リビングの入り口や、広いウォークインクローゼットの扉など、空間のシンボルとなるような場所に設置されることが多いです。
利便性とデザイン性を両立した「親子ドア」

親子ドアは、普段使用するメインの「親扉」と、必要に応じて開ける小さな「子扉」の2枚で構成された開戸です。 普段は親扉だけを開閉して出入りし、大きな荷物を運ぶ時や人の出入りが多い時には子扉も開けて開口部を広げることができます。
玄関ドアやリビングの入り口によく採用されており、デザインのアクセントにもなります。片開き戸よりも広く、両開き戸よりも省スペースで設置できる、利便性とデザイン性を兼ね備えたバランスの良いドアと言えるでしょう。
知っておきたい開戸のメリット
多くの住宅で採用されている開戸には、引き戸にはない様々なメリットがあります。デザイン性だけでなく、機能面での利点も理解することで、より納得のいくドア選びができます。ここでは、開戸が持つ主なメリットを3つご紹介します。
高い気密性と遮音性を確保しやすい
開戸は、ドアを閉じたときに枠と扉がぴったりと密着する構造のため、引き戸に比べて気密性や遮音性、断熱性に優れています。隙間が少ないため、音漏れを防ぎたい寝室や書斎、子ども部屋に適しています。また、冷暖房の効率を高める効果も期待できるため、省エネの観点からもメリットがあると言えるでしょう。
デザインやハンドルの種類が豊富
開戸は、世界中で広く使われているドアの形式であるため、デザインのバリエーションが非常に豊富です。 シンプルなものから装飾的なもの、ガラスがはめ込まれたものまで、多種多様なデザインから選ぶことができます。
また、ドアノブやレバーハンドルといった取っ手の種類も豊富で、ドア本体との組み合わせによって、自分好みのスタイルを演出しやすいのも大きな魅力です。
引き戸に比べて比較的安価に設置可能
一般的に、開戸は引き戸に比べて構造がシンプルです。引き戸のようにレールや戸を引き込むためのスペースが不要なため、部品代や施工費を比較的安く抑えることができます。 新築やリフォームにおいて、コストを重視したい場合には大きなメリットとなるでしょう。
ただし、選ぶドアの素材やデザイン、機能によっては価格が大きく異なるため、予算に合わせて検討することが重要です。
知っておきたい開戸のデメリット
多くのメリットがある一方で、開戸にはいくつかのデメリットも存在します。特に、設置スペースや安全性に関する点は、導入前に必ず確認しておくべき重要なポイントです。デメリットをあらかじめ理解し、対策を考えることで、より快適な住まいづくりに繋がります。
開閉のためのスペースが必要になる
開戸の最大のデメリットは、ドアを開閉するためのスペース(可動域)が前後に必要になる点です。 そのため、ドアの近くに家具や物を置くことができず、デッドスペースが生まれてしまいます。廊下などの狭い空間に設置すると、人がいる場合にドアを開けにくくなったり、窮屈に感じたりすることがあります。
設置を検討する際には、ドアの可動範囲を事前にしっかりと確認することが不可欠です。
風にあおられて急に閉まる危険性
開戸は、窓を開けている時などに強い風が吹き込むと、風圧にあおられて勢いよく「バタン!」と閉まってしまうことがあります。 この現象は「あおり」と呼ばれ、大きな音で驚くだけでなく、ドアや壁が損傷する原因にもなります。
また、閉まる瞬間に指などを挟んでしまう危険性も伴うため、特に小さなお子様がいるご家庭では注意が必要です。ドアストッパーや、ゆっくりと閉まる機能が付いたドアを選ぶなどの対策が有効です。
ドアの向こう側の人と衝突する可能性
ドアを開けようとした際に、向こう側にいる人に気づかず、ぶつかってしまうという事故も起こり得ます。 特に、廊下の角や人の往来が多い場所に内開きのドアを設置する場合は注意が必要です。ドアにガラスのスリットが入っているデザインを選ぶと、向こう側の人の気配を感じやすくなり、衝突のリスクを減らすことができます。
家族全員が安全に暮らすために、設置場所の動線を考慮したドア選びが重要です。
後悔しないための開戸の選び方のポイント

ここまで開戸の種類やメリット・デメリットを見てきましたが、最終的にどのドアを選ぶべきか、迷ってしまう方もいるかもしれません。ここでは、数ある選択肢の中からご自身の住まいに最適な開戸を選ぶための、3つの重要なポイントを解説します。
設置する場所の広さと動線を確認する
まず最も重要なのは、ドアを設置する場所のスペースと、家族の生活動線です。開戸には必ず開閉スペースが必要になるため、ドアを開けた時に通路を妨げたり、家具にぶつかったりしないかを確認しましょう。 また、右開きと左開きのどちらが使いやすいか、内開きと外開きのどちらが安全かなど、日々の動きをシミュレーションしながら検討することが大切です。
部屋の用途やデザインとの調和を考える
ドアは、部屋の機能性やインテリアの印象を大きく左右する要素です。例えば、プライバシーを重視したい寝室には、遮音性の高いものや光が漏れにくいデザインのドアが適しています。リビングなど、家族が集まる空間には、採光が取れるガラス入りのドアを選ぶと、明るく開放的な雰囲気を演出できます。壁紙や床材の色とのバランスも考えながら、部屋全体のコンセプトに合ったデザインを選びましょう。
安全性や機能性にも注目する
毎日使うドアだからこそ、安全性や機能性にもこだわりたいところです。小さなお子様やご高齢の方がいるご家庭では、軽い力で開閉できるレバーハンドルや、指挟みを防止する機能が付いたドアがおすすめです。 また、急に閉まるのを防ぐソフトクローズ機能や、施錠機能の有無なども確認しておきましょう。
デザインだけでなく、家族全員が快適で安全に使える機能が備わっているかどうかも、重要な選択基準となります。
ソフトクローズの仕組みとは?メリット・デメリットから選び方まで徹底解説 » 中尾製作所オンラインショップ
まとめ
この記事では、開戸の主な種類から、それぞれのメリット・デメリット、そして後悔しないための選び方のポイントまでを解説しました。開戸は、日々の暮らしの快適性や住まいの印象を大きく左右する重要な建具です。
ぜひ本記事を参考に、ご自身のライフスタイルや住まいの空間に最適な一品を見つけてください。